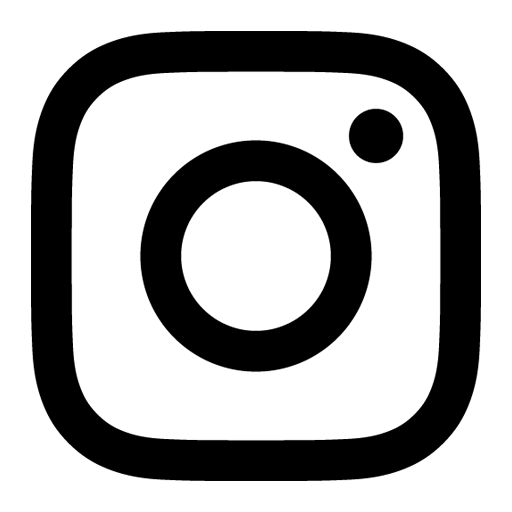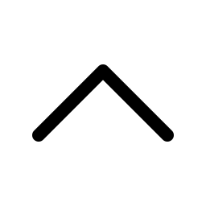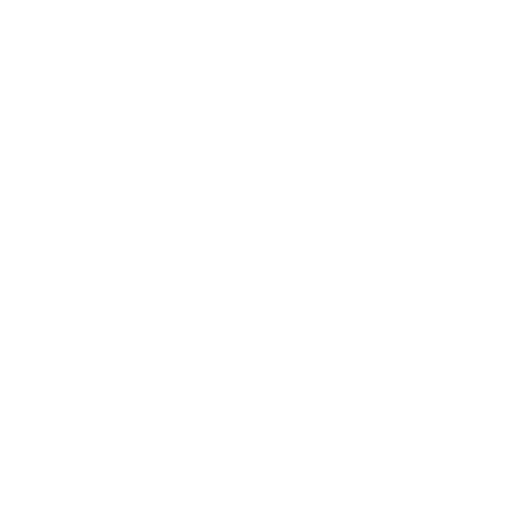薪ストーブの準備はお早めに!安全に「火のある暮らし」を楽しみましょう

こちらは、当社が施工したTさまのお宅(https://www.takuyou.jp/works/works-373/) のダイニング。窓辺には薪ストーブの燃料である薪が積まれています。薪山越しに望む雪景色は、とても風情がありますね。

薪ストーブは、上段が炉室、下段がオーブンになったイタリア製を採用しました。断熱・気密ともに、竣工した当時の国の基準を上回る住宅性能を持つTさま邸。
そのため、補助暖房のエアコンだけで朝晩も十分暖かいそうですが、「部屋の中に火があると落ち着くんです」(Tさま)と薪ストーブを主暖房として使っています。奥さまもオーブンでピザやパウンドケーキ、キッシュなどをよく作っているそう。薪ストーブはTさま邸の主役と言える存在です。
* * *
そんなTさま邸のような“火のある暮らし”を安全で快適に楽しむには、冬が来る前にいくつかの準備が必要です。

その一つが薪の確保。すでに割られた薪を購入する方法もありますが、玉切りされた原木を調達してきて自分で割るのも、薪ストーブと暮らす儀式と語るオーナーさまもいらっしゃいます。キレイに割れたときの爽快感や楽しさも、薪割りの醍醐味なのかもしれません。

そして一番大切なのがしっかりと乾燥させること。乾燥が不十分だと暖まりにくいだけでなく、不完全燃焼を起こしてしまいます。日当たりがよく風通しのよい場所でしっかりと乾かしましょう。

続いては、ストーブ本体の掃除です。炉内にたまっている煤(すす)や灰はすべて取り除きます。

ガラス扉の内側のヒモ(ガスケット)も劣化していないか確認を。紙幣1枚を挟んで扉を閉めた時、引っ張ると抵抗なく紙幣が取れるようであれば交換の時期です。

ガラスを含む扉回りの掃除もポイントです。密閉性を保つため、灰・燃えカスはすべて除去。灰でガラスが曇ってしまった場合は、専用クリーナーを使うと取れやすくなります。

そのほか、塗装の剥がれやサビの発生、部品の劣化がないかも確認してください。
※上記5点のストーブ写真は、薪ストーブ専門店フランシスさん公式サイト(https://fransis.jp/)より

煙突の煤落としも入念に。このように、煙突の途中を外してビニールをつけてスタンバイ完了!

足元に十分気をつけながら、いざ屋根の上へ。専用ブラシの先に柄をつなぎながら煙突の中に差し込んでいき、何回か上下させて煤を下に落とします。

すべての掃除・点検を終えた後は、薪ストーブに火を入れてみましょう。
シーズン始めは、いきなり高温まで焚き上げず、少しずつ温度を上げる「慣らし焚き」がおススメです。こうすることで、急な熱膨張によるストーブの破損が防げます。

以上、薪ストーブの基本的なお手入れ方法をご紹介しましたが、メーカー・機種によってやり方が異なったり、掃除や部品交換をするには難しい箇所があると思います。その際には、購入したお店などに相談してみてください。
もうすぐ長い冬がやってきます。寒さの厳しい季節こそ、薪ストーブライフを楽しみたいですね!